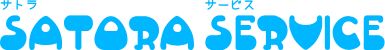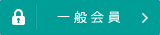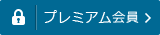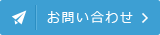TOPICS
災害③
こんにちは、今年は国内でも海外でも大きな山火事が頻発していますね 
さて、少し間が開いてしまいましたが、前回は災害医療についてお話ししたと思います。
本日は、災害時の外傷や疾病についてお話ししたいと思います。
地震等の自然災害の発災時は打撲、骨折、切断、裂創、挫創等の様々な外傷が多発します。
創が土等に汚染され感染を助長させる可能性があり、流水で創と周囲の皮膚を洗浄+ガーゼ保護が必要です。資材がなければ、できる限り清潔にしておくことが重要です。
災害の種類により、発生頻度の高い疾病は異なります。
阪神・淡路大震災やR6年の能登半島地震では建物倒壊での圧死が最も多く、東日本大震災では津波による溺死が最も多かったです。
発災当初は外科系疾患が多く、避難生活が長引くと内科的疾患や精神疾患が多くなるなど、同じ災害であっても時間経過やフェーズにより変化します。
災害時によく見られる疾病は以下が挙げられます。
・圧挫症候群(クラッシュ症候群):瓦礫等の重量物に骨格筋が長時間(一般的には2〜4時間ですが、1時間でもあり)圧迫され、筋組織に虚血や損傷が生じ、圧迫が解除されたときに全身状態が急変し心停止を起こす場合がある
・熱傷:災害時に火災が発生すると広範囲熱傷や有害ガスの吸引で気道熱傷が多発することがある
・溺水:液体が気道内に吸引され窒息や呼吸障害をきたす
・熱中症と低体温症:被災地ではライフラインの途絶などにより屋内の空調設備が十分に機能しなくなり、夏季は熱中症、冬季は低体温症が発生しやすい
・深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症:避難生活に伴う活動量低下が下肢の血流停滞や、ストレスによる交感神経亢進状態による血液凝固能亢進や、水不足やトイレに行くのを避けるために生じる脱水や、災害時の受傷による血管内皮の損傷により発生しやすい
また、災害時に注意しなければならない感染症は以下が挙げられます。
・破傷風:土壌にあり、時に致死的になる場合がある
・津波肺:溺水だけでなく汚染水の吸引による治療抵抗性の肺炎となる場合がある
・避難所における集団感染:集団生活による様々な感染症がある(黄色ブドウ球菌感染症、百日咳、COVID、疥癬、結核、インフルエンザ、感染性腸炎、麻疹、肺炎、食中毒、水疱等)
災害による死亡は家屋倒壊・火災等による直接的な被害だけでなく、避難生活の疲労・ストレス、ライフラインの途絶、医療機関の機能停止等の環境の変化により新たな疾患の発症や持病の悪化により死亡することがあり、これを災害関連死といいます。
能登半島地震を含め、近年の災害では多くの災害関連死が報告されています。
災害特有の疾病もあり、災害医療に関わる場合はしっかり学習する必要がありますね!
ではまた!